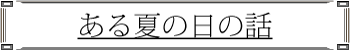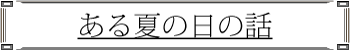
遠くから祭囃子が聞こえてくる。祭りの会場になった校庭には多くの影がひしめき、その校庭の外周にずらりと屋台が並ぶ。
そんな胸躍る喧噪の中を、私は友人と肩を並べて歩いて行く。
ふと、私の視線が吸い寄せられるように一点に向いた。
「どしたの?」
私がいきなり立ち止まったため、数歩先行する形になった友人が振り返る。黙って指差す私。怪訝そうにそちらを見やった友人が、げっ、といやそうな顔をする。
[それ]は一目でこの世のものでないとわかる異形。屋台と屋台の間から見える校庭の片隅、祭りの賑わいから隔絶された闇にそれはいた。
じっとそちらを見る私たちに、屋台のおじさんが不思議そうに自分も覗き込み、首を傾げながら仕事に戻る。
彼には見えていない。当たり前だ。ああいうものは、私や友人のように、特別な眼の持ち主しか見ることはできない。
「ほっといて行こうよ」と促す友人を振り切って、私はそれに近づいた。おじさんが気味悪そうにこちらを見ていたが、そんなことはどうでも良い。
[それ]は泣いていた。意味は全く理解できないけれども、それでも泣いているのが私にはわかる。その声があまりにも悲しげで、胸が締め付けられそうに寂しい色を帯びていたから。
背後に友人の気配。なんだかんだでついて来てくれるのはこういう時の私が絶対に譲らないと経験から知っているからか、それとも彼女もやはりこの異形が気になるからだろうか。
「どうしたの?」
私が声をかけると、[それ]はびくりと声を詰まらせ、おびえたように後ずさる。
「大丈夫、怖がらなくていいから。迷子になっているんでしょう?私がお家に帰してあげる」
震える[それ]を抱きしめる私を、淡い光が包み込む。
子供のころから、望まずして私には異界の存在を感ずる力があった。
誰に訴えても信じてもらえず、ただ奇異な視線で見られるだけだった。
父も、母も、たくさんの同世代の子供たちの眼にも映らない、異質との接点。
それは絶望的なほどの孤独と恐怖。自分が狂っているのではないかと追い詰められた私は、両親に泣いて眼を潰してくれと頼み込んだほどだった。
そんな私を救ってくれたのは祖母だった。
とうとう療養という名目で祖母の下に厄介払いされた私は、誰とも交わらずに心を閉ざし、祖母のことも無視し続けた。
祖母は何を追及するでもなく、毎日温かいご飯を作り、柔らかな声で私に語りかけ、その度必ず私の頭を撫でてくれた。
その優しさに日々殻は溶けてゆき、ある日私は、堰を切ったように祖母に眼のことを語った。
泣きじゃくりながら要領も得ない私の話を、祖母は真剣に聴き、信じてくれた。そして私にこう言ったのだ。その眼を持ったことには意味がある、と。
それから私は、時間をかけてこの力を受け入れていった。異形の存在も忌避しなくなり、同じ眼を持つ友人に出会い、迷い込んできた異形達を彼らの世界へ帰してやる術を得た。
祖母はそんな私を、昨年亡くなるまで、ずっと見守っていてくれた。
だから、放っておくことなんてできない。かつての私のように孤独に泣くこの子を、かつての祖母がしてくれたように、助けてあげたかった。
光が強まるにつれて、[それ]の輪郭がぼやけていく。二度とこの子が迷いませんように。そう祈りながらそっと放した。
ふわりと浮かんだ[それ]が光に溶けていく。無事に帰れそうだと安心していると、こちらに向かって何か言った。言葉はわからなくても、ありがとう、と、そう言ってくれているのがわかった。だから私も、笑って答える。
「どういたしまして」
光が弾けて消える。そこにはもう、異形の姿は無かった。
「ご苦労さん」友人が笑いかけてくる。それに満足げに頷いて、私は歩き出した。
「それにしても今回のあれはヘンテコな格好だったねえ」
ぶるぶると全身の毛を逆立てながら、口の付いた触手を震わせる友人。
確かに今回のはこれまで見た中でもとびきり奇異な姿をしていたが、私は祖母の蔵書の中で全く同じ姿のお化けを見たことがある。眼が二つで鼻と口が一つずつ。それらは全部、一つしかない頭部にあり、二本ある足で歩き、様々な道具を器用に操るという五本指の手。
全身にある目玉のうちのいくつかを友人に向け、三つある口の左側を使ってそう伝える。
「へえ! 何ていう名前?」
頭から生えた目を丸くする友人に教えてあげた。
「[ニンゲン]って、いうんだって」
遠くから祭囃子が聞こえてくる。祭りの会場になった校庭には多くの影がひしめき、その校庭の外周にずらりと屋台が並ぶ。
そんな胸躍る喧噪の中を、私は友人と肩を並べて歩いて行く。
これは何の変哲も無い、ある夏の日の話……
[おしまい]