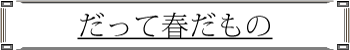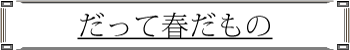
それはもう誰も文句をつけようのない夏のこと。
夏を知らないロシア人(偏見)でも、連れてきて立たせるだけで万言を弄するよりも遥かに深く夏というものを理解するであろう灼熱の中、何故か隣にいる俺の幼馴染は
「春だね」
などとぶっ飛んだことをおっしゃる。
「だって、春だよ?」
蝉啼いてるぞ。
「春だもん」
陽炎が立ってる。
「春なのね」
汗ダラダラだぞ。
「春だから! ほら桜!」
葉桜だろうが。
「いいのっ! 春ったら春なの!!」
何が気に入らないのかむすっとしたままドスドス先行く我が幼馴染。
こいつの頭のネジが緩んで外れたのはここ最近のことで、少なくとも今年晴れて腐れ縁の神通力により同じ高校に受かってからしばらくはめちゃめちゃ機嫌が良かった。
朝は毎日起こしてくれるし弁当は作ってくれるし、その度キラキラした太陽みたいな笑顔を浮かべていて、なんかいいなあこういうの、と思っていたのに、その輝きは実際の日差しの強さに反比例してどんどん曇り、最近は雨、時々雷雨という天気から回復する気配はない。
公園の片隅、紫陽花がやたら咲いている一角のところで、目の前の般若が振り返った。頑なに間服をまとい、全身を汗で濡らしながら
「ほんとに、覚えてない……?」
と、一転して泣きそうな顔で問うてくる。
一週間前に妙に切実そうに同じ質問をされて、うん、とよくわからず頷きグーで殴られた身としては、答えに窮して身を強張らせる。
こちらのそんな様子に、む~っとふくれた般若は
「もういい!!」
ズバアン! と打撃と叫びを残して去って行った。今日は鞄だったか。仰向けに倒れたまま、ぼんやりと思う。
くすくすと笑い声が降ってきた。
痛む顔を押さえながら体を起こすと、正面に妙な少女が立っている。
おかっぱ頭で年の頃は八、九歳。晴れているのに黄色い雨合羽を着て、その手には傘のような巨大な葉っぱの茎を握っている。
やーい怒られた、ところころ笑う少女。
「誰だお前……」
少女の態度に憮然としてみせるが、そんなことなどお構いなしにスタスタ近づいてきて、ひょいとこちらを覗き込む。
「約束忘れた悪い子誰だ」
じっと見つめてくる瞳の深さに怯みながら、一つの単語が意識にかかる。
約束……? 誰の、誰との……
少女はまたころころと笑いながら続ける。
「そう、約束。あなたとあの子がした誓い。あなたはすっかり忘れてて、あの子はずっと覚えてた。今でもそれを待ってるの」
ちょっと待て。何だそりゃ。あいつとした約束なんて…
「思い出して。言葉と行いは、どっちが足りなくてもダメなの。あの子のことが大切なら、紡いだ言葉に見合う行動が要るよ」
少女が手にした葉っぱを俺に向けてくるくると回した。
「ちゃんと思い出してあげてね」
その言葉を聞きながら、俺の意識がゆっくりと落ちた。
それはまだ中学に上がる前のことだった。いつものように遊んでいた俺を突然あいつが呼び出し、まさにあの紫陽花の一角で告白したのだ。
唐突過ぎたし恥ずかしかったし、なによりもまだガキだった俺は、テンパった末に
「お、大人になったら……」
と答え
「それっていつ?」
と尋ねるあいつに
「あれだ! こーこーせーになった春だな! 今度は俺から言ってやるよ!」
とごまかしたのだ。
……ああ、あれか。だからあいつはあんなに春だ春だってこだわって……
――思い出せたかな?
心に響いた声に頷く。ありがとな、と言ったところで意識が戻る。そこにはあの日と同じ紫陽花が咲いていて、少女の姿はどこにも見当たらなかった。
翌日、紫陽花のそばで思いを伝える昨日の少年を見ながら、手にした葉っぱをくるくると回しながら少女が笑う。
「雨降って地固まるって言うし、雨降らすのと地面固めるのは私の仕事だよね」
まあ今回雨降らしてないけどね、と一人ごちる視線の先、見つめあっていた二人が互いを抱きしめたのを見て、おおっ、と少女は歓声を上げた。
「いやあ、春だなあ!」
返事をするように、ジジっと、蝉が一声啼いた。 (おしまい)