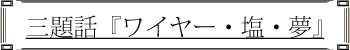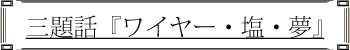
最近妙な夢を見る。自分は深い深い穴のそこに立って、遥か頭上に一番星みたいにぽつんと見える光をただじっと見つめている、そんな夢。
困ったことにそれが夢であるという自覚はとてもはっきりしていて、目が覚めてその夢から脱出するまで、ひたすらまんじりと光を睨み続ける羽目になる。おかげで今日もひどく辛い朝を迎え、死にかけみたいな顔で教室に現れた僕を、隣の席に座っていた少女が訝しげに見ている。
「どうしたの。寝不足?」
その博覧強記っぷりに教師陣から一度脳味噌がどうなってるか見てみたいとまで言わしめた少女である。もしや夢に関しても何ぞ造形深くあらせられるかもしれないと、僕はかくかくしかじか事情を話してみることにした。ふむふむと彼女は真剣に話を聞いてくれて
「んー、小っちゃい頃に穴に落ちて出られなくなったとかいう経験は?」
「無い」
「三度のご飯より穴が好きとか」
「そんな異常性癖も無い」
「ぽっかぽかの日に干したてのお布団でするお昼寝よりも穴が好きとか」
「比較対象の問題じゃない! っていうかえらく具体的だな!」
好きなの昼寝? と訊く僕に、うん! とキラッキラの笑顔で答える彼女。
「そっかやっぱり無いかー。あはは、まあそうだよね、何か憑いてるもん」
「……はい?」
「憑いてる。ばっちり」
「な、何がでしょう……」
「何だろうねーこれ。気配がするだけで姿は見えないから、君に、というか、君の夢に憑いてるんだろうね」
珍しいねー。獏とかかな。と、ふふ~と笑う彼女をがっしとつかんで懇願する
「何とかしてください」
彼女はえー、と首を傾げ
「君の夢の中のことまでわからないよー。原因突き止めてくれたら手伝ってあげなくもないけどね。というわけではいこれ」
と、彼女はごそごそと鞄から何か取り出して僕の手に乗せる。
「何これ」
「うん、ワイヤーと、そっちの包みは塩だね」
「何でワイヤーロープなんて持ってるの!?」
「夢の世界からの脱出にはワイヤーだよ。知らない? 海腹○背」
あれルアーじゃなかったっけ。しかもその設定なかったことにされたんじゃ……
「塩は? 撒けばいいの?」
ううんと彼女は首を振る。
「それね、特別製の塩で、すんごい辛いの」
「だから?」
「目を覚ますにはもってこいだよ」
その言葉と同時に予鈴が鳴る。気遣いのありがたさに涙が出た。
その晩またも同じ夢が現れる。しかしいつもと違うのは、「ちゃんと寝る時に枕元に置いて寝ること」と彼女から厳命されたワイヤーがしっかりと握られていることだった。
「海○川背ね……」
明らかに長さが足りてないそれを試しに頭上に向けて放ってみると、みるみる伸びて先端が穴の縁にしっかりと引っかかる。
「えーと、確かこう……」
結構やり込んだ件のゲームを思い出してぐっと体重をかけてみると、金属製のはずのワイヤーはゴムのようにたわむと、カタパルトよろしく凄まじい勢いで僕を上方向に加速させた。
「うわわわわわ……っとお!?」
思ったほどの衝撃も無く着地し、見事に穴から脱出した僕は、振り返って飛び出してきた穴を見た。それはどこかで見たことのある古井戸で
「これ、うちの近所の……」
歩いて十分もかからない、今は空家になっている民家の敷地内にあるものだ。子供の時分、面白がって覗き込んでこっぴどく叱られたのを覚えている。
「何でここ?」
と思っていると、井戸の中から消えそうなほどにか細い声がした。耳を澄まし、その声の主に思い当たった瞬間、頭の中で全て繋がった。僕は急いで行動を起こそうとしてはたと気づく。
「ここ夢の中じゃん!」
一刻も早く目覚めて現実世界の方の井戸に駆け付けたいのに、夢から覚められない。念じてみたり踊って見たりほっぺたをつねってみたりしたけれど、何の効果も無かった。
焦りに焦っていると、ふとポケットから小さな白い包みが出て来た。中には荒い粒の白い粉。
――目を覚ますにはもってこいだよ
「そういうことか!」
一気に口の中に含んだ。味は訊かないで欲しい。おかげで目は覚めたけれど……
早朝にもかかわらず、彼女は快く応えてくれた。井戸に下りられる道具、という電話越しの無茶な頼みに、ぶっといワイヤー製の縄梯子を持って来てくれた彼女は、下りて行く僕を不思議そうに見ていたが、戻って来た僕の腕に抱かれたそれを見て目を輝かせる。
「おお、猫ちゃん! 君の家の子?」
「違うよ。ここの家の、無くなったばあちゃんと僕が可愛がってた野良。ここ何日か見かけないと思ってたんだ」
「なるほどねー。君に助けてって言ってたんだね」
知り合いの獣医を叩き起こして診てもらったところ、衰弱はしているものの問題は無いらしい。数日預かってもらうことになってほっとした僕は、帰り道に彼女に謝った。彼女のくれたワイヤーは、夢から覚めると何故かきれいさっぱり消え失せてしまっていたからだ。
「そういうものだからいいよー全然。それにしても猫ちゃんが助けを求めるなんて、君は優しい人なんだねー」
良い子良い子と頭を撫でられ真っ赤になる僕に、「そんな君に言っておきたいことがあるんだ」と、僕の正面に向き直る。
「な、何……?」
朝の静謐な空気とそこにある彼女の微笑に、何だか変な想像をしてしまう。彼女はそんな僕の内心のドギマギも知らず、うん、と一つ頷くとこう言った。
「まだ何か憑いてるよ」
「………………はい?」
「うん。憑いてる。ばっちり!」
唖然とする僕を気にせずくるりと回れ右した彼女は、うきうきとした足取りで歩き始める。ふふ~と肩越しに笑顔を見せて
「今度は獏だといいねー」
「何とかしてください!!」
朝のしじまに、僕の悲鳴が響き渡った。
(おしまい)